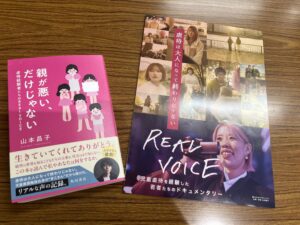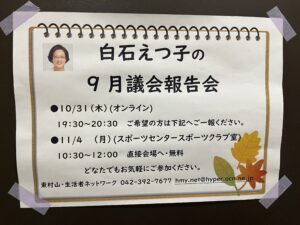10/24 豊中市児童発達支援センター視察報告
 令和6年10月24日
令和6年10月24日
豊中市児童発達支援センターの視察報告
これまで市内にあった福祉型児童発達支援センター豊中市立あゆみ学園、医療型児童発達支援センターしいの実学園で培ってきた障害児療育の機能、アセスメント実績を新・児童発達支援センターに移行し、運営が開始されています。
豊中市の障害のある子どもへの支援のイメージ
◎めざす姿
「すべての子どもが、地域社会の一員として自分らしく豊かに生き子どもと家族が地域で主体的に社会生活を営む」
◎基本理念
子どもの人権の尊重
子どもの最善の利益の保障
子どもが個性や能力を発揮できる機会の提供
きづく⇔つなぐ⇔支えるを共通項目としている
新・児童発達支援センターにある機能別の事業展開
1.障害児通所支援事業
(児童発達支援事業・放課後等デーサービス事業(民間委託事業)親子通所・単独通所・就園就学後小集団親子教室義務教育終了後の発達障害児を対象とした放課後等デーサービス事業を受給者証を基本におこなっている。
2.子ども療育相談
(1)相談支援事業(基本・計画相談)
社会福祉士3名で相談に当たる
(2)障害児等療育支援事業(来所相談・在宅訪問支援・療育技術指導)在宅訪問支援は、無料で利用でき、学校に入ることも可能な建付け
(3)保育所等訪問支援
(4)保護者支援講座(ペアレントトレーニング・ペアレントメンター他)要保護児童対策として基幹相談支援センター7箇所で中核になる事業者所を指定対応
ペアレントトレーニングは保育資格者に受講必須
(5)発達支援親子講座
PT・ST・OT訪問の際、医療職連携で地域支援を行っている
(6)発達支援巡回訪問
ASD(高機能自閉症)一人遊びは上手など特徴を共有する
民間全施設を訪問し、情報連携に努める
(7)障害児通所支援事業所訪問
(8)障害児通所支援事業所へのスーパーバイズ・コンサルテーション事業 支援者研修はリアルと動画配信を用意、研修を必須とし、資質向上を図る
(9)言葉と身体の相談(子育て支援センターほっぺ)
子育て支援の中核施設で子どもの発達における不安などに相談対応
(10)発達支援講座・相談会(地域子育て支援センター)保護者支援講座など相談会を実施
(11)医療的ケア児訪問保育
ヘルパーによる訪問介護
一緒に保育し、一緒に子育てを楽しむようサポート
(12)診療所
障害の区別なく、乳幼児期から青年期まで幅広い診療体制がある
医学的リハビルテーションは、あらゆる療法を肢体不自由児や知的障害児等の成長に合った療育を提供している
管理医師(小児科医)、嘱託医、整形外科医各1名、児童精神科医2名
高年齢児・不登校支援、自傷行為などアウトリーチを生かし、学校現場を観ることも定期的に実施。個々のアセスメントから、スモールステップ後方支援を心掛けている。
民間委託の居場所事業団体との情報連携し、18歳までを支援。18歳以後で引きこもり等場合は、若者支援所管につなぎ、サポステ、切れ目のない支援を図っている。分離教育は分離社会の入口とならないよう、地域の子は地域で育つを基本に療育に当たっている。
豊中市は、障害を特別とせず、差別から偏見を生まない土壌が同和教育等から培われてきた歴史があります。そのため、当センターのめざす姿は、子どもの人権の尊重、子どもの最善の利益の保障、子どもが個性や能力を発揮できる機会の提供となっていることも、多様性、社会的包摂とされるインクルーシブなまちづくりを実践していることも理解できました。東京都が掲げる心のバリアフリーに留まらず、障害等を理由に社会から排除されないインクルージョンなまちづくりに変えていける可能性を今回の視察の成果を生かしていきます。
最後に豊中市で子育てしてきた保護者からこれまでとこれからについて交流をおこなった。強度行動障害のあるご長男。発達に加え、腎臓機能障害を患うご次男、ご長女は白血病を患っています。その中でも、母親ご自身は、障害児を抱える保護者の助けになればと保育士の資格を取得し、障害児の療育を含めた保育に従事しています。やはり、通常学級で共に学び、共に育つ姿勢が貫かれていることで、義務教育を終えても、豊中市に住み続けていける地域コミュニティが形成されているとも感じました。
#分けない教育
#豊中市南桜塚小学校
#同和教育
#インクルーシブ教育システムへの提言
#橋本校長と中田先生
#あゆみ学園
#しいのみ学園
#豊中市児童発達支援センター