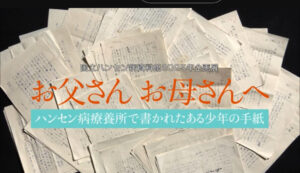9/13 楽しい学校は大人が導き,子どもが創る。
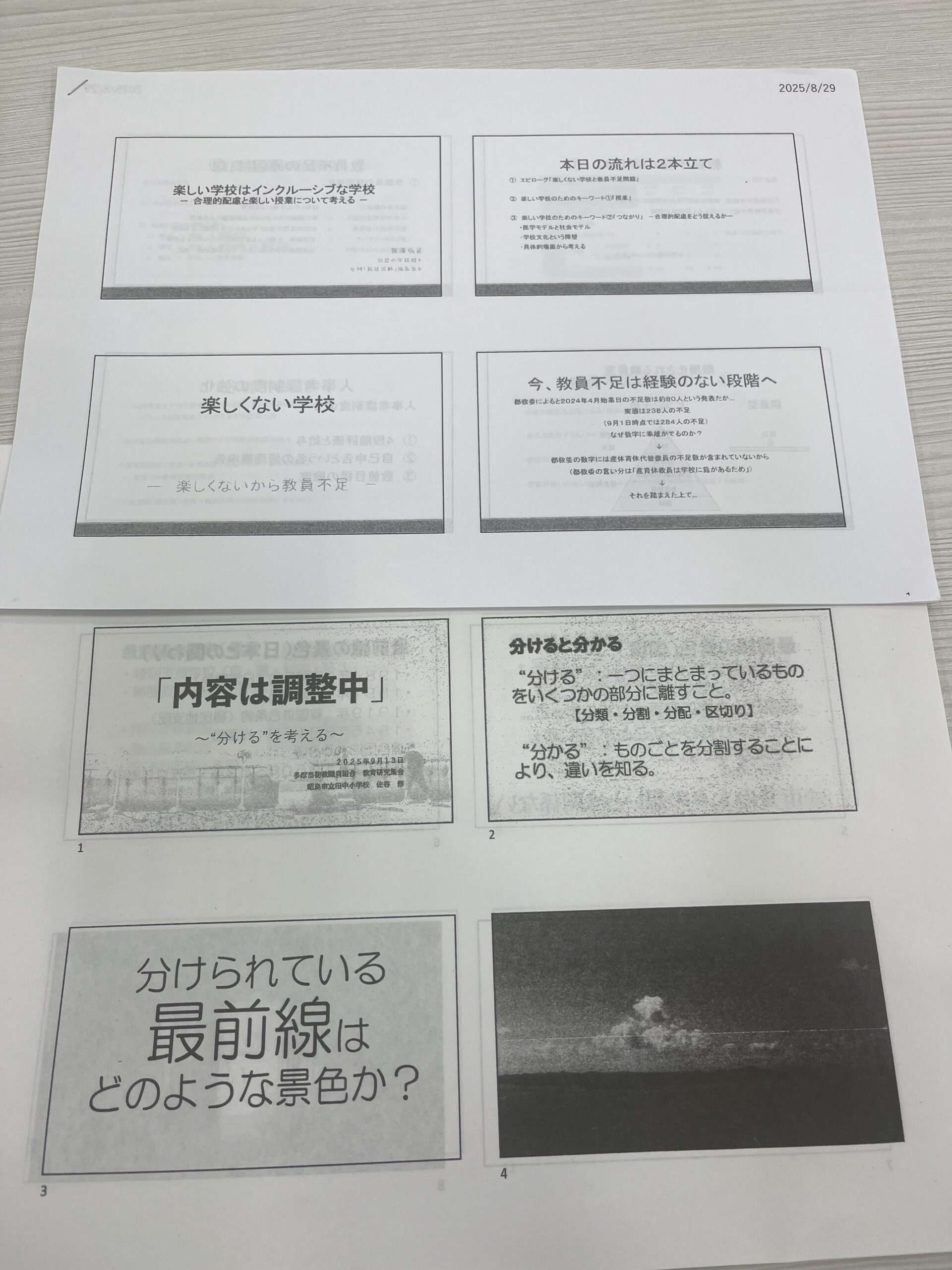 9/13
9/13
多摩教研研修会、中身の濃い時間でした。
宍戸監督による”風は生きよという”を、
学校に当たり前に共に学んできていない障害をまずは知ることから、学校教材として皆さんに観てほしいです。
海老原宏美さんのご両親の生き方に共感します。娘さんの人生もご自身の人生も,障害があるからと犠牲にしない、諦めない思いが伝わりました。海老原さんが将来人の助けが必要となること、ご苦労されるであろうことを見据え、あえて通常学級を選択した。
国立市という土地柄もあるのでしょう。
その時の経験が後に大変な思いをしながらも、生きる糧になっているんだなと。
近隣の住宅に訪問看護のヘルパーさん募集チラシをヘルパーさんと配布して回るなど、つながりを意識しているのがわかる日々の行動がありました。
今,国立市に特別支援学校から復籍交流を継続してる子どもさんが中学生になるのですが、学校にエレベーターが未整備のため、段差解消機チェーンウェイターを付けられないかをDETの石川莉利さんが仲介役として、業者と市の担当所管,議員有志で話し合いが持たれました。合理的配慮の観点からも実現して欲しいです。エレベーターができれば、やがて全ての人に有効になります。
実態ができれば、他の地域にも良い連鎖が起きるのではと考えます。
海老原宏美さん著”私が障害者でなくなる日”の本も図書館に置いているなら積極的に読み聞かせをしないと社会が障害を作り出している結論には至らないです。
障害児者は,”可哀想な人,見えているのに見えない、見ようとしない存在”のままです。
東村山市でも,医療的ケア児は35人居ます。
通常学級を選択した2人の子ども達のおかげで、共に学ぶ環境はできています。
重症心身障害児にこそ,社会を変える力があります。
この子らを世の光に!
糸賀一雄氏のこの言葉を大事にしてます。
澤田先生、佐谷先生,宮澤先生の共通項は,誰もが当たり前に持つ基本的人権の尊重であり,保障する社会のあり方をまずは学校から実現しようとするものと理解しました。
わからなくても楽しい授業、間違ってもいいから,自ら考えて導き出した答えを教員が褒める。子どもも大人と同じく今を生きる権利の主体と共通理解にすることが今,求められています。
これは、中々認識しにくいことです。
教員は指導する立場,人格形成を図るなど教え込まれていますから。木村泰子さんの言葉を借りればヒエラルキーは要らない。普通の子はいない。分離でなくて共生を!
まずは足元から変えていけるよう,微力ですが,当事者意識と共感,対話を意識していきます。貴重な学びの時間ありがとうございました。
#多摩教研
#新学習指導要領
#インクルーシブ教育システム
#インクルーシブ教育
#フルインクルーシブ
#合理的配慮