7/21(月曜) 第4回 「日本のインクルーシブ教育の課題と 「共育」の可能性について」

7/21 “人権,権利について学ぼう!”
“東村山市に子どもの権利条例を作ろう!”
第4回
「日本のインクルーシブ教育の課題と
「共育」の可能性について」

講師は、電動車椅子ユーザー杉浦貢さん,
ご自身のご経験から、
日本のインクルーシブ教育は現状では、
うまくいかないと感じている。
身体に障害があり,普通校と特別支援学校両方に通ったことで、コスト至上主義が優先され、時間と手間をかけた丁寧な個別指導は敬遠されがち。
先生の言うことを聞きなさい!
ルールに同調しなさい!
均一的、画一的な学校運営は、障害の有無に関わらず、子ども一人ひとりの特性に合わせたきめ細かい指導を困難なものにしている。
先生方に、個々の子どもさんをじっくり見守る余裕かない!働き方改革がここにも必要!
これこそがインクルーシブ教育がうまくいかない根源的な理由に思える。
令和の時代においても、日本の教育現場の根底には、自己責任、自助努力、旧来の根性論や精神論がいまだに存在しているとおもえてならないと。
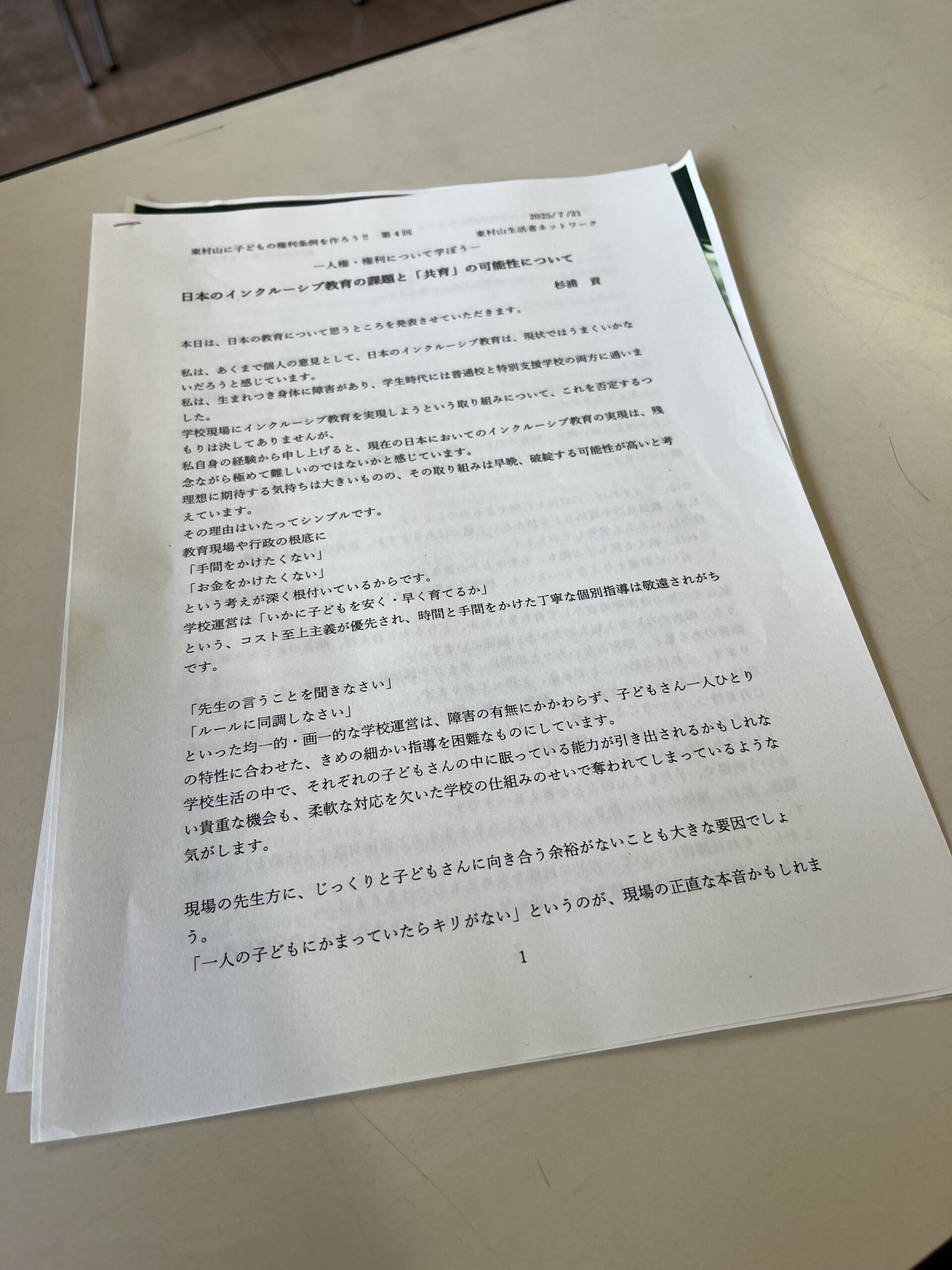
教育の本質は、共育!
教える側も学ぶ側も、本来は上下の差などなく、対等な立場で同じ時間を共有し、互いに影響を与え合う。
「人はそれぞれ違う」の
前提で子ども達と向き合う。
学びの主体は子ども!
どう学びたいか,何を学びたいかを
大人が聴く度量が必要。
意思決定支援を基本としながらも、自分の意見は聞かれずに,本人不在で事は進む。
知的年齢と身体年齢のアンバランスが顕著なのが障害児の特性。障害の種類や度合いも違うのだから,特別支援学校に当たり前の専門性を持つOT.PT.ST、言語聴覚士等の登用も普通学校に必要ではないか。
インクルーシブ教育は、単に障害のある子とない子が同じ空間にいることではない。
学校で自分が行っている講和は、互いの違いを認めようとする視点を持ち、対話を通して理解を深めようと努める、障害を理解したかという結果でなく、試行錯誤のプロセスを経ることに得難い価値がある。
違いを学ぶ機会,知る機会を得られないことで、差別や偏見はより強化されてしまうから。繰り返し学び合うことが重要。
会場からは、大阪府豊中市のインクルーシブ教育を実践する小学校に視察に行った際、
電動車椅子ユーザーの教員が出迎えてくれた。もちろん学校内は改築されエレベーターが設置されていた。特別支援学級併設だが、原学級に補助教員が「入り込み」の手法を取っている。まさに,「共に学ぶ,共に育つ」を実践する成功事例が共有された。
お題目だけで、インクルーシブ教育を語るなら,うまくいくはずはないでしょう。
「共に学び,共に育つ」と言う観点が、より
多くの人に広まり,根を張ることを願って
止みませんと杉浦貢さんは締めている。
自閉症・情緒特別支援学級の教員、看護師、多種多様な障害児者と共に暮らす家族、障害当事者,電動車椅子製造者、区議会議員などなど多くの方々が課題を持ち、ご参加してくださり、人権,権利を学び合う時間を共有できました。
杉浦貢さん、ご自身のご経験を語って頂き,ありがとうございました。
これからも、当事者意識と共感、対話を繰り返し、人権擁護や権利の尊重を基本とし、差別や排除を生まない地域づくりを進めていきます。
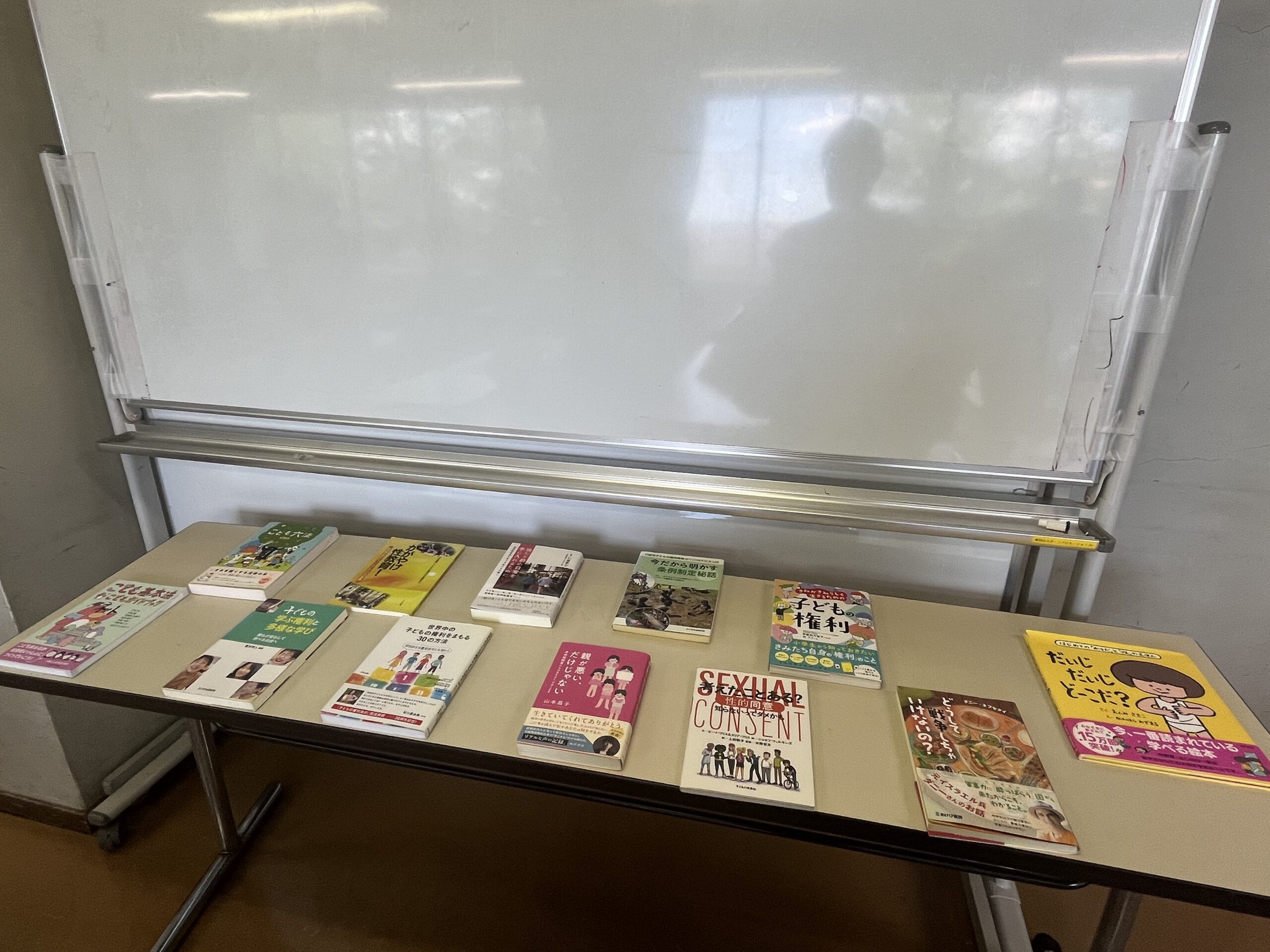
#子どもの権利条約
#こども基本法
#障害者差別解消法
#バリアフリー法
#インクルーシブ教育
#インクルーシブ教育システム

